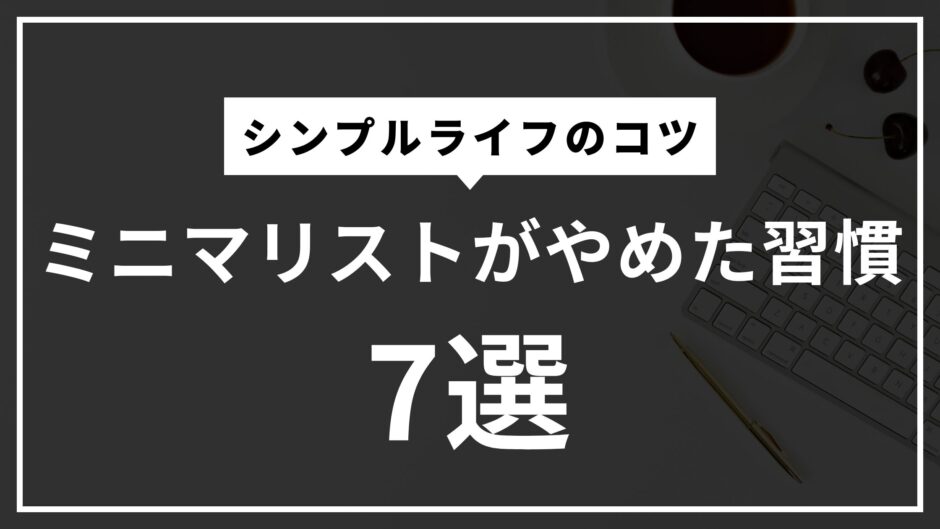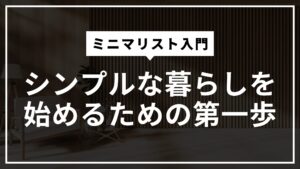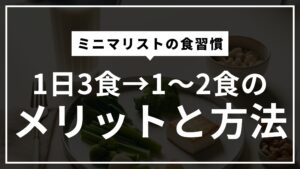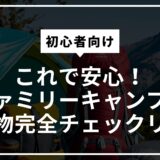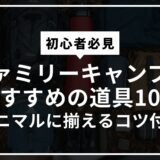朝からバタバタ、夜はクタクタ…。子育て中の毎日、気づけば自分の時間なんてゼロ。
「もっと余裕を持って過ごしたい」「心にゆとりがほしい」——そんなふうに思ったこと、ありませんか?
私もそうでした。でも、何かを「増やす」より「やめる」ことで、暮らしはぐっとラクになりました。
この記事では、ミニマリストが実際にやめてよかった【7つの習慣】を紹介します。どれも子育て中の今だからこそ手放したい、小さな“無理”や“頑張りすぎ”。
「やめる」ことで、心と時間に余白が生まれ、子どもにも、そして自分にも、もっと優しくなれるようになりました。
読み終わる頃には、あなたの暮らしにも余裕のヒントが見つかるはず。
がんばる毎日に、ちょっとだけ「手放す勇気」を。
シンプルな暮らしを始めたい方はこちらの記事から
買い物の“ついで買い”
ミニマリストを目指す人が最初に見直すべき習慣の一つが、「ついで買い」です。
これは、スーパーやコンビニ、ネットショップなどで本来の目的以外のモノを「なんとなく」買ってしまう行動のこと。
例えば、「牛乳だけ買うつもりだったのに、お菓子や雑誌まで買ってしまった…」という経験、誰にでもあるのではないでしょうか。
ついで買いが招くもの
この小さな習慣が積み重なると、以下のような問題が生じます。
- お金の無駄遣い:必要ない出費が増える
- モノが増える:収納スペースがすぐにいっぱいになる
- 管理の手間:使わないモノが増えると、片付けや掃除が面倒になる
ミニマリストは、こうした「衝動的な消費行動」が生活のノイズになることに気づき、やめました。
実践例:買い物リストの活用
ミニマリストが実際に取り入れているのが、「買い物リストを事前に作る」というシンプルな方法です。
- スマホのメモ帳アプリや紙のメモに、買うものをあらかじめ書き出しておく
- リストにないものは一切買わないルールを自分に課す
- ネットショッピングの場合は、いったんほしい物リストに入れて24時間以上寝かせてから購入判断する
このようにルールを明確にすることで、感情に流されず、必要なモノだけを選ぶ力が養われていきます。
このように「ついで買い」をやめるだけでも、生活が驚くほどシンプルになります。
食習慣を変えたい方はこちらの記事へ
SNSでの無目的なスクロール
スマートフォンを手に取り、何気なく開いたSNS。
気づけば30分、1時間とスクロールし続けていた──
そんな経験はありませんか?
ミニマリストがやめた習慣の中でも、多くの人が挙げるのがこの「SNSの無目的な閲覧」です。
SNSの“見過ぎ”がもたらすもの
SNSは便利で楽しいツールですが、使い方を誤ると次のような影響があります。
- 時間を奪われる:1日15分でも、1ヶ月で約7.5時間のロス
- 情報疲れ:必要のない情報まで次々と流れ込む
- 自己肯定感の低下:他人のキラキラした投稿と自分を比べてしまう
特に、「自分は何もしていない」「もっと頑張らなきゃ」と無意識にプレッシャーを感じることもあります。
ミニマリストはこのような“見えないストレス”に気づき、SNSの使い方を見直しました。
実践例:デジタルミニマリズム
デジタルミニマリズムとは、テクノロジーを「意図的に」「選択的に」使う考え方です。
ミニマリストたちは以下のような工夫をしています。
- スマホのホーム画面からSNSアプリを削除 or フォルダーにしまう
- アプリの通知をOFFにする
- SNSにアクセスする時間を決める(例:朝と夜の15分ずつ)
- 「見る目的」を決めてから開く(例:レシピ検索、友人の近況チェック)
こうした小さな工夫で、「なんとなく見ていた時間」が、「自分のための時間」に変わります。
SNSは生活を便利にする道具ですが、主導権を握るのは“自分”です。
おすすめ書籍
比較する癖
「隣の芝生は青く見える」とはよく言ったもの。
SNSや日常生活で、他人の暮らしぶり、仕事ぶり、収入、家族関係などを見て、つい自分と比べてしまうことはありませんか?
この「比較する癖」も、ミニマリストが手放した大きな習慣の一つです。
比較が生む“見えないストレス”
他人と自分を比べることは、一見モチベーションのように思えるかもしれませんが、実際には次のような悪影響を及ぼします。
- 自己肯定感の低下:「自分には何もない」と感じてしまう
- 過剰な消費行動:「あの人みたいになりたい」と必要以上の買い物をしてしまう
- 常に焦りを感じる:自分のペースで生きることが難しくなる
特にミニマリストが重視するのは、「本当は必要ないものまで持ってしまう原因になる」という点です。
他人の持ち物や暮らしを基準にしてしまうと、自分にとっての“本当に必要なもの”がわからなくなります。
実践例:自分軸で考える
ミニマリストたちは、比較のループから抜け出すために、次のような方法を取り入れています。
- 「理想の暮らし」ではなく「自分にとって心地よい暮らし」を明確にする
- 感情が動いたときは、「なぜそう感じたか」を内省する習慣を持つ
- 他人の生活を見たら、羨むのではなく「参考」にとどめる
また、他人の価値観ではなく、自分の価値観を見つめ直すことで、必要のないモノ・コトが自然と減っていきます。
他人との比較を手放すと、不思議なほど心が軽くなります。
おすすめ書籍
予定を詰めすぎる
「せっかくの休日だから、あれもこれも予定を入れよう」
「空いている時間があると、何かしなきゃもったいない」
そんな風にスケジュールをぎっしり埋めてしまうことはありませんか?
ミニマリストがやめた習慣の中でも、「予定を詰めすぎる」ことの見直しは、生活全体に大きな変化をもたらします。
詰め込みすぎの弊害
予定をたくさん入れると一見「充実している」ように見えますが、次のような問題が起こります。
- 常に時間に追われる感覚:余裕がなく、気持ちが急かされる
- 疲れが取れない:身体も心も休む間がない
- 自分の感情に気づけない:内面に向き合う時間がなくなる
これらは、一見すると生産的な行動の裏で、ストレスや慢性的な疲労感を生む原因になっているのです。
実践例:「余白」を意識した時間の使い方
ミニマリストが大切にしているのは、「予定のない時間=ムダな時間ではない」という考え方です。
- 1日のスケジュールにあえて“空白”を残す
- 予定の後には「クールダウン時間」を設ける(移動・休憩など)
- 「今日は何もしない日」と決める日を作る
こうした余白のある時間が、頭と心の整理につながり、新しいアイデアや感情に気づく余裕を生み出します。
予定を詰めこむ生活から一歩引くことで、本当に必要なことがクリアになります。
おすすめ書籍
マルチタスク
現代の忙しいライフスタイルでは、「ながら作業」が当たり前になっています。
仕事をしながら音楽を聴く、食事中に動画を見る、スマホをいじりながら人の話を聞く……。
これがいわゆるマルチタスクです。
一見、効率が良さそうに思えるこの習慣。
しかしミニマリストたちは、このマルチタスクをやめることで、生活の質が大きく向上したと語ります。
マルチタスクがもたらす問題点
実は、マルチタスクには以下のようなデメリットが潜んでいます。
- 集中力の低下:人間の脳は「同時に複数の作業」を処理できない
- ミスの増加:注意が分散することで、確認不足や失敗が起こりやすくなる
- 脳疲労の蓄積:タスクの切り替えが増えると、知らず知らずのうちに脳が疲れる
結果として、「時間を有効に使っているつもりが、実は効率も満足度も下がっていた」ということになるのです。
実践例:シングルタスクのすすめ
ミニマリストが取り入れているのは、「一つのことに集中する=シングルタスク」という考え方です。
- 作業の前に、「今、自分がやるべきことは何か?」を明確にする
- タイマーを使って集中時間(例:25分)を区切る(ポモドーロ・テクニックなど)
- スマホは視界から遠ざける or 機内モードにする
このような工夫により、作業がスムーズに進むだけでなく、**「やり切った感」や「充実感」**がしっかりと得られるようになります。
マルチタスクを手放し、一つひとつのことに丁寧に向き合うことで、生活に落ち着きと深みが生まれます。
おすすめ書籍
不要な人間関係の維持
「昔からの付き合いだから」
「誘われたら断りづらいから」
そんな理由で、実はもう心が離れている人間関係をなんとなく続けていませんか?
ミニマリストたちは、モノと同じように人間関係にも“取捨選択”が必要だと考えています。
エネルギーを消耗する関係を続けることは、自分自身をすり減らす行為だからです。
不要な人間関係が与える影響
合わない人や無理して関わる人間関係は、次のような悪影響をもたらします。
- ストレスの増加:会うだけで疲れる、気を使いすぎる
- 時間の浪費:本当はやりたいことに使える時間が奪われる
- 自己評価の低下:ネガティブな言動に引きずられやすくなる
人間関係は“目に見えない荷物”になりやすく、ミニマリズムを実践する上で無視できないポイントです。
実践例:距離の取り方を見直す
ミニマリストたちは、関係を一方的に切るのではなく、「心地よい距離感をつくる」ことを意識しています。
- 連絡頻度を無理に保たない(返信に時間をかけてもOK)
- 義務感で参加していた飲み会や集まりは断ってみる
- 「一緒にいて疲れる」と感じたら、その気持ちを大切にする
また、自分にとって大切な人との関係には、より丁寧に向き合うようになります。
結果として、人間関係の“質”が上がり、人付き合いがもっとシンプルで心地よいものに変わっていきます。
人間関係を見直すことは、自分の時間と心を取り戻す大きな一歩です。
おすすめ書籍
完璧主義
「もっときれいにできたはず」
「100点じゃないと意味がない」
そんなふうに、すべてにおいて完璧を求めていませんか?
ミニマリストたちがやめた最後の習慣は、完璧主義です。
一見、向上心の表れに見えるこの考え方ですが、実は多くのストレスや行動のブレーキになっていることがあります。
完璧主義がもたらす落とし穴
完璧主義にとらわれると、以下のような悪循環に陥りがちです。
- 始められない:100点を目指しすぎて、最初の一歩が踏み出せない
- 終わらない:何度も見直して時間ばかりが過ぎる
- 疲れやすい:常に「もっとできるはず」と自分を追い込んでしまう
また、完璧を求めるあまり、他人にも厳しくなり、関係にギクシャクしたり、自分の感情を押し殺したりすることもあります。
実践例:「70%でOK」と考える
ミニマリストたちが取り入れているのは、「ちょうどいい加減」を見つけるという考え方です。
- 「とりあえずやってみる」ことを優先し、完成度は気にしすぎない
- 家事や仕事も「7割できていれば合格」と自分に許す
- 「できたこと」に目を向け、できなかったことを責めない
特に家の片づけや生活の整え方は、「完璧」を求め始めると終わりがなくなります。
ミニマリズムでは、「心地よく暮らせることが最終ゴール」と考えるので、必要以上に頑張ることはありません。
完璧を求めるのをやめると、毎日の生活が驚くほど軽く、やさしくなります。
まとめ
ここまで、ミニマリストが手放した7つの習慣をご紹介してきました。
- ついで買い
- SNSの無目的なスクロール
- 他人との比較
- 予定を詰めすぎること
- マルチタスク
- 不要な人間関係の維持
- 完璧主義
これらはすべて、心のノイズや時間の浪費を生み出す原因です。
ミニマリズムとは、モノを減らすことだけでなく、「無意識に続けてきた習慣」や「自分にとって本当に必要のない考え方」を見直すことでもあります。
大切なのは、一気に変えるのではなく、自分に合ったペースで、できるところから少しずつ見直していくこと。
1つの習慣をやめるだけでも、驚くほど生活がスッキリし、心に余裕が生まれます。
もし今、何かに疲れていたり、暮らしを変えたいと思っていたら――
まずはひとつ、あなたにとって「いらないかも」と感じる習慣を手放してみてください。
そこから始まる変化が、あなたのシンプルライフへの第一歩になるかもしれません。